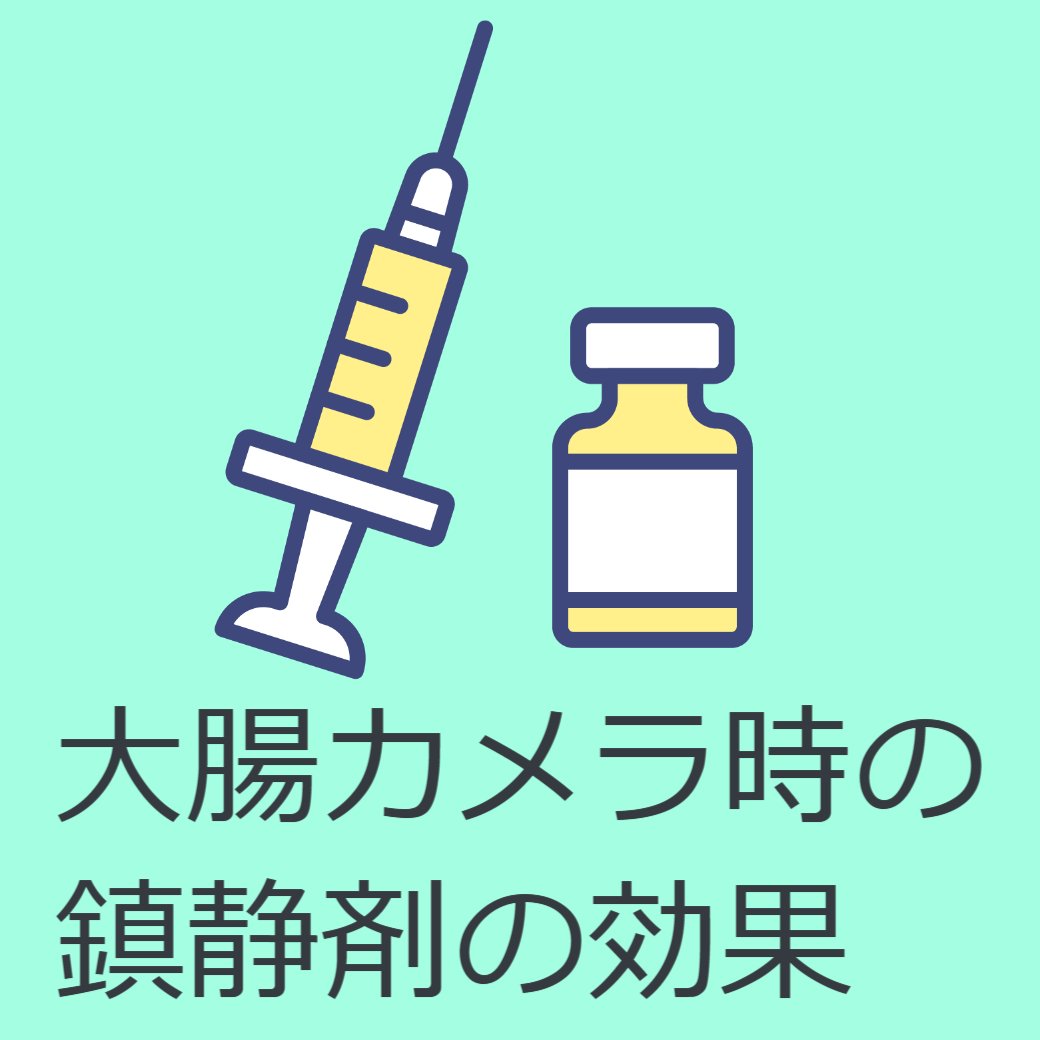2024年6月24日

こんにちは。
梅雨に入り、ジメジメした毎日ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
今回は腫瘍マーカーについてブログを更新しましたので、良かったら最後までお読みください。
腫瘍マーカーについて
たまに「血液検査で癌が分かりますか?」とか、「癌マーカーがあるって聞いたのですが、検査出来ますか?」とか質問される事があります。
おそらくは「腫瘍マーカーの事を言っているのだろうな」という所までは分かりますが、質問に対する答えには困ってしまいます。
と、いうのも「腫瘍マーカーで癌があるのが分かるか?」と聞かれれば、「分かると言えば分かる」し、「分からないと言えば分からない」という謎かけの様な答え方になってしまうからです。
しかも、詳しく話そうとすると、専門的になりすぎる上に、話が長くなり、聞く方も、話す方もクタクタになりやすい話題の一つです。
ですが、よく話題に出る話ですので、今回はできるだけ噛み砕いた説明をしてみようと思います。
腫瘍マーカーとは
もともと、腫瘍マーカーとは「癌がある人」の腫瘍の勢いを見るために開発された検査です。
正常細胞ではほとんど生産されず「腫瘍細胞で生産される物質」や「腫瘍があることによって生体内で産生する物質」で腫瘍が縮小すれば下がり、増大すれば上がるという性質を持った物質に腫瘍マーカーという名前を名付けています。
その性質を利用して医療現場では手術後の評価や抗癌剤の効果判定に使われていますが、健康診断の場で使用するとなると、数値の個人差が問題になってきます。
どういう事かというと、普通の人なら「だいたいこのぐらい」という目安となる数値を、「癌もない」のにいきなり越えてしまっている場合があります。実際、このケースで紹介される事が多く、各種精密検査を行っていましたが、癌がない事も結構ありました。
また、マーカーの種類や個人によっては、「手術が必要なサイズの癌がある」にもかかわらず、腫瘍マーカーが「全く上昇しない」場合もあります。
この様に個人個人で目安となる数値に幅があるため、非常に使いにくい特性を持っていますが、「癌があると分かっている同じ個人」に対しては有効で、もともとの数値から、治療が効けば低下するし、効かなければ上昇するため、癌に対して有効な治療法を探す上で重要な指標となります。
では、健康診断での腫瘍マーカーの扱いをどうするかというと、同じ個人を数年から十数年検査をする事で、「横ばいだから多分、大丈夫」とか、「徐々に増加しているから全身を検査してみましょう」と推測する事ができます。
実際、ずっと正常値範囲内ではあったものの、少しずつ腫瘍マーカーが上昇していたために、精密検査を勧めて、癌が見つかったという経験をした事はあります。
ただ、ここにも個人差がでるので、「どれぐらい増加していれば検査をする」のか、また、「レントゲンやエコー、胃カメラなどの精密検査をどこまで検査をするか」というのが難しく、統一した意見はありません。
例えば、もともと、「10」の人が「1000」になったら、さすがに「検査をしましょう」と説明します。
しかし、「100」だったら? 「50」だったら? 「20」だったら? と、どこで検査をするのかのラインを引く事が非常に難しく、医師によっても見解はマチマチでしょう。
しかも、そんな腫瘍マーカーが、有名なモノだけで30種類もあるとなれば、どの腫瘍マーカーを「どれぐらい数」を、「どれぐらいの間隔」ですれば良いのか、なんて分かるはずもなく、検査をしたものの、「多分、大丈夫ですね」ぐらいしか話しようがないのが現実です。
で、あるのであれば、消化器内科の端くれとしては、消化器部門の癌であれば、腫瘍マーカーより早く見つけられる可能性のある検査を「胃カメラをしましょう」、「大腸内視鏡をしましょう」、「腹部エコーをしましょう」と、勧めるわけです。
と、言う訳で、癌が心配な皆さん、
「胃カメラをしましょう」
「大腸内視鏡をしましょう」
「腹部エコーをしましょう」
最後までお読み頂きありがとうございました。