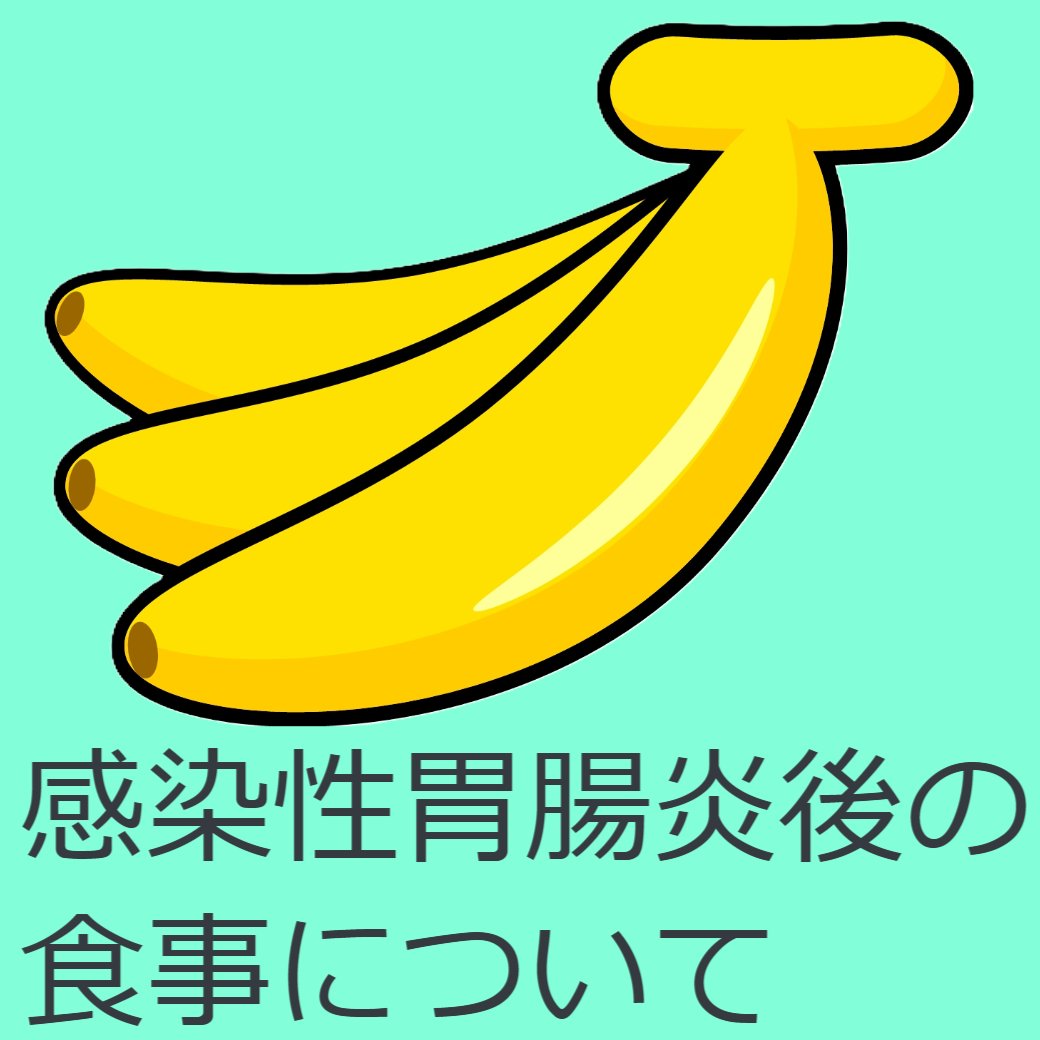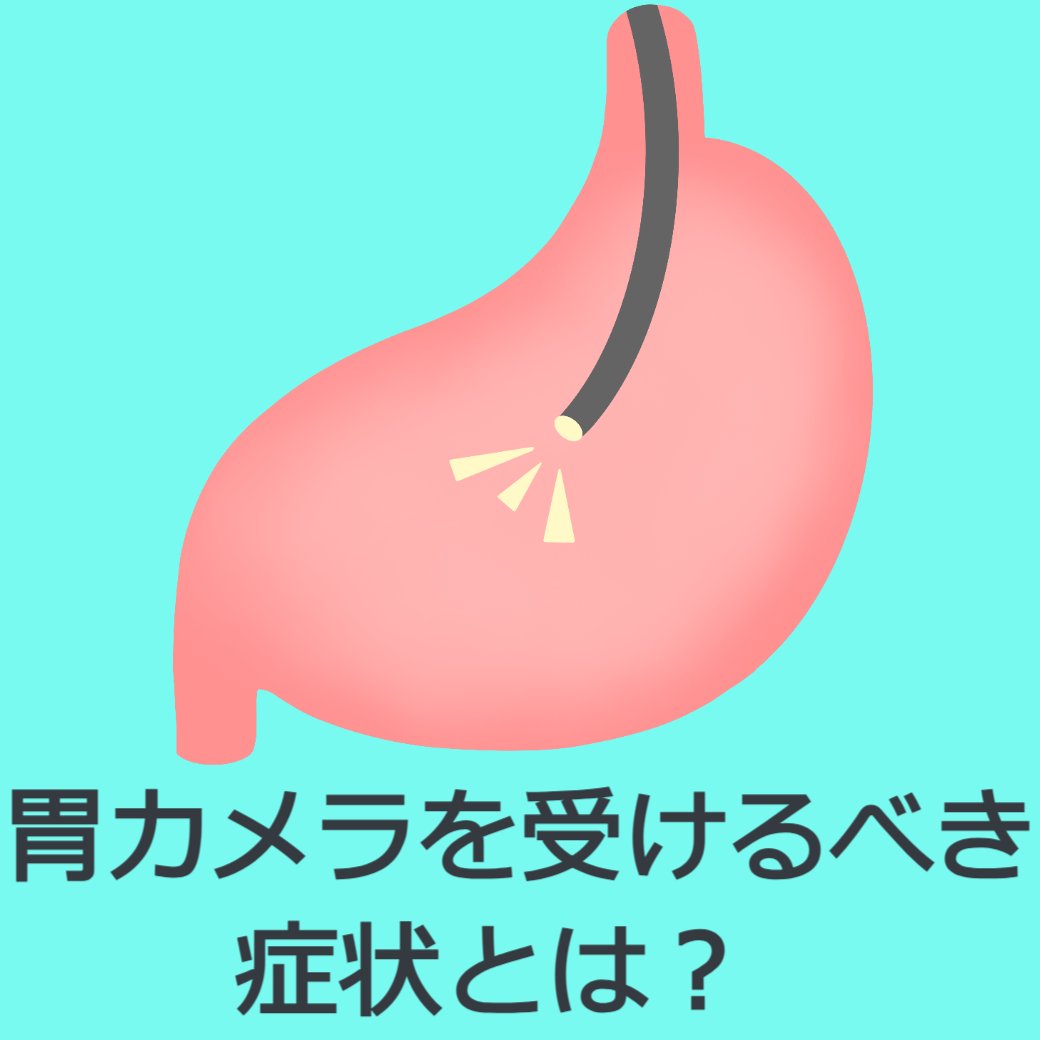2025年10月06日
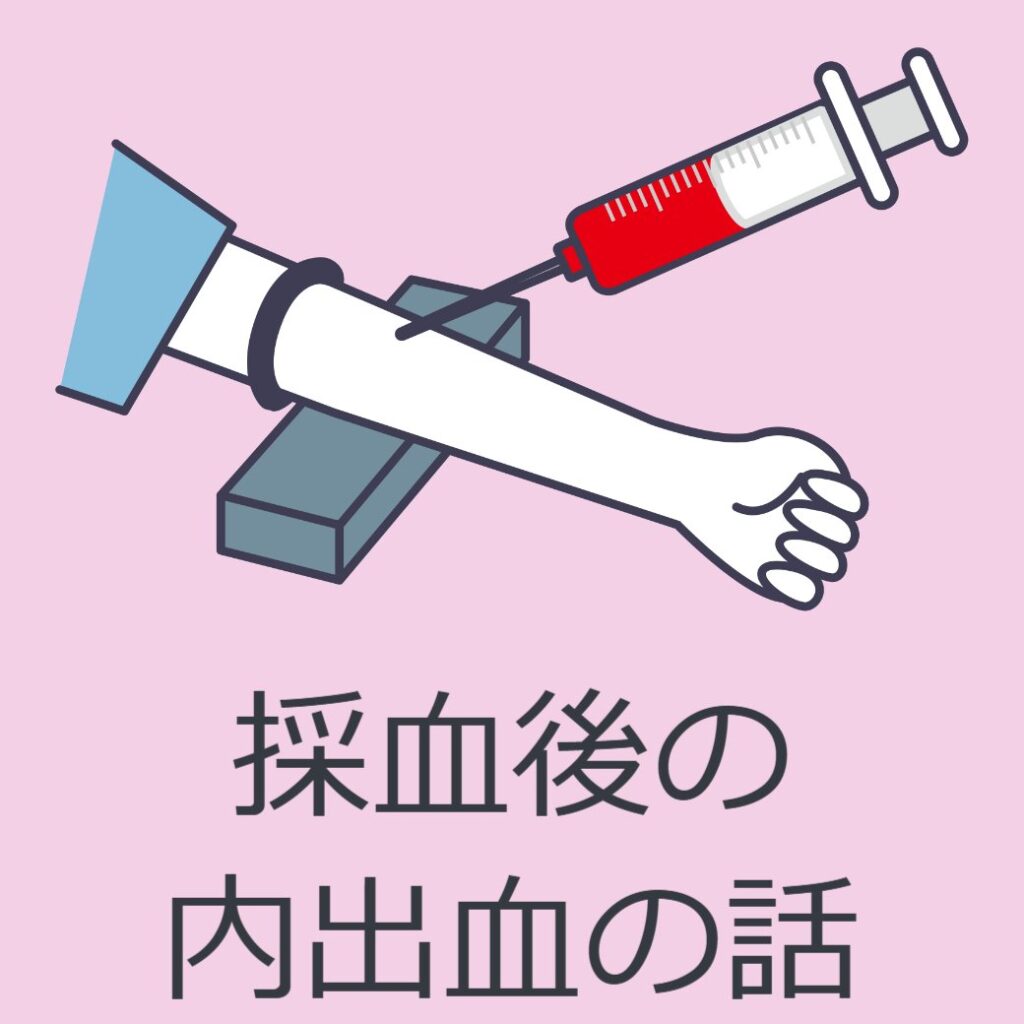
こんにちは。ひらたクリニックです。
10月に入り朝晩涼しく感じるようになってきました。まだまだ日中は暑い日が続くようなので、寒暖差で体調を崩されないようにお気を付けください。
採血後に内出血になったことがある方、結構いらっしゃるのではないでしょうか。私自身も内出血になったことがあります。
そこで今回は、採血で内出血が起きる原因についてお伝えしたいと思います。よければ読んでみてください。
内出血とは?
一般的には『あざ』と呼ばれます。医療用語では『皮下出血』です。
採血後に内出血が起きてしまう原因は、主に4つあります。
1.血管を探している間に血管外に血液が漏れた
一般的に採血を行う際、針を刺す前に上腕の部分を圧迫し、針が刺さりやすい血管を探します。
ただ、人によってはせっかく血管を見つけても針を刺したあとに血管が逃げてしまうことがあります。その際、一度刺して穴が開いた血管から血液が漏れてしまい、内出血を引き起こす場合があります。
2.採血中に腕が動いてしまった
採血中に腕が動いてしまうと、血管や針の位置がずれてしまうことがあります。
どちらも位置がずれると、穿刺していない部分にも傷がつく可能性があり、その傷ついた部分から血が漏れて内出血が起こってしまうのです。
3.採血中の針の固定が甘かった
採血中は、針が血管を貫通しないように角度を浅めにして穿刺します。ただ、浅めに穿刺する際は針をしっかり固定しないと穿刺部位とは別の部分に針が刺さってしまいます。
それにより穿刺部位ではない箇所から血液が漏れて内出血が起こってしまうのです。
4.採血後の圧迫が足りなかった
採血後にしっかり圧迫をしないと、穿刺した部位から血液が漏れて内出血を起こしてしまいます。採血後に「しっかり押さえていてください」と伝えても、揉んでしまう人がいます。揉んでしまうと皮膚と血管の間に血液が入り込み内出血したような跡が残ってしまいます。
内出血になりやすいのはどんな人?
内出血になりやすい方は以下の通りです。
・高齢者
・血管が細い人
・血管が深い人(パッと見た目では見えない人、指で触れてもわからない人)
・採血後の止血圧迫が足りない人
・採血部分を揉んでしまった人
・血液をサラサラにする薬を服用している人
内出血にならないためには
内出血を起こさない為には以下の点を注意して頂ければと思います。
・止血を十分に(5分以上は止血圧迫を行う)すること
・しっかりと針を刺した部分を押さえること
・止血時には揉まないこと
・採血した腕に負荷をかけすぎないこと
内出血ができても自然に改善します
採血部の出血が止まったかは目視では確認できません。したがって、十分な止血すると内出血、あざの予防になると考えられます。
もし内出血を起こしてしまっても、約7~10日ほどで色は落ち着いてきます。
内出血後の皮膚の見た目は、青紫 → 赤紫 → 黄色というように色が変化し、自然に吸収されていきます。
痛みが強い場合は、冷却(アイスノンにガーゼタオルを巻いて)すると和らぐこともあります。
採血時、その後にしびれがある場合は?
穿刺時に神経が血管近くに走行しているような部位は極力採血を行わないようにしていますが、血管の浮きが分かりにくい場合にはそういう部位を選ばざるを得ません。
その場合非常に稀ですが細い皮神経に針が当たって損傷する場合があります。
採血時や注射時に指先までしびれを感じた場合はすぐに教えてください。
その場合は穿刺を中止させていただきます。
針を抜いた後もしびれが続いたり、比較的長期に渡ってしびれが続く場合があります。
長い方ですと1か月程度違和感が続く場合があります。
いかがでしたか?
採血後に止血圧迫をお願いするのですが、まれに自分はすぐに血が止まるから大丈夫、と圧迫されない方がいます。
また稀に、止血できておらず、血が漏れている方がいらっしゃいます。
皆様にお願いしたいのは5分以上はしっかり圧迫をしていただきたいということです。
杖をついている方、圧迫を行いながらの歩行が難しい方、サラサラの薬を服用されている方、大きな荷物を持っていて圧迫が難しい方は、止血ベルトを巻かせていただいています。それ以外のご自身で止血圧迫ができる方はしっかり圧迫をしていただきたいと思います。
当院での採血後や注射後の内出血がひどい、痛みがある、しびれがある場合はご相談いただきたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。