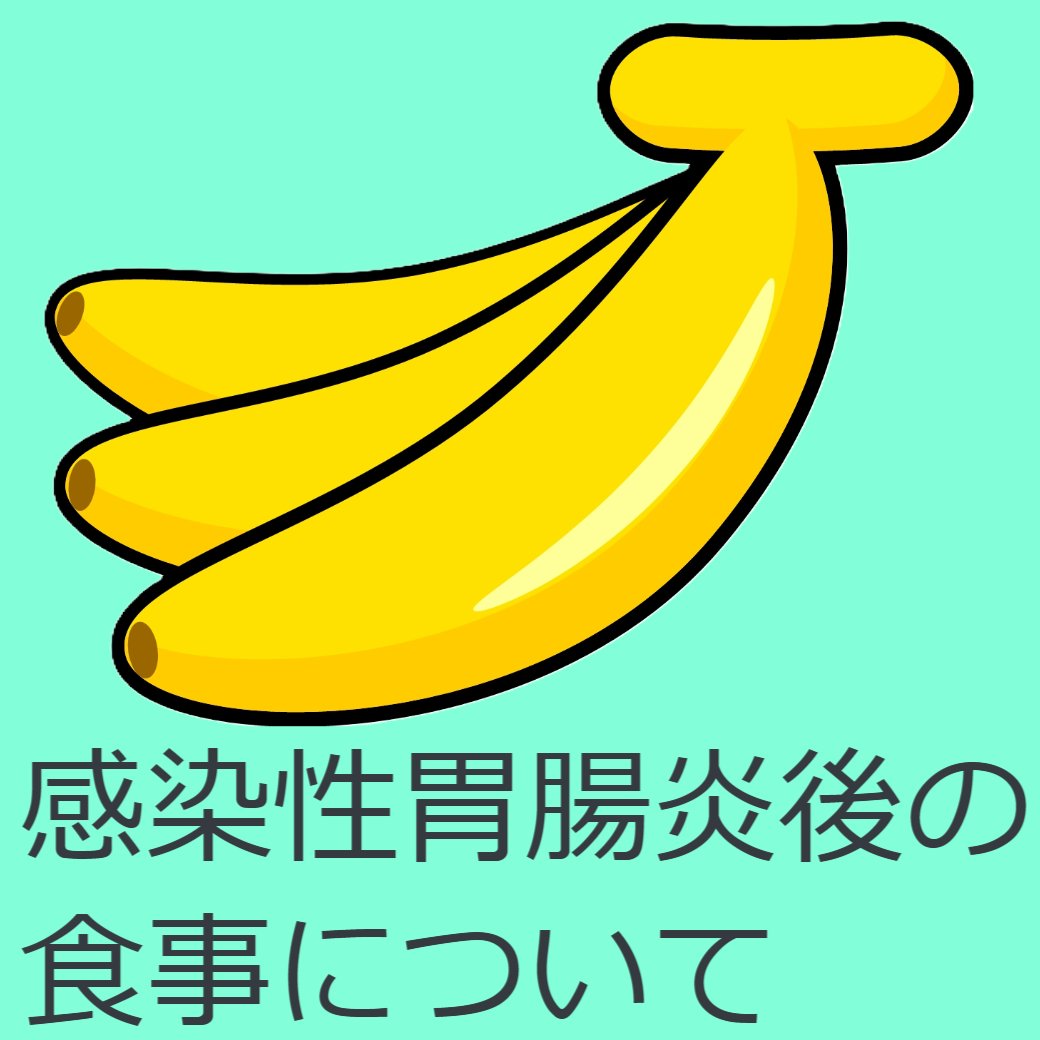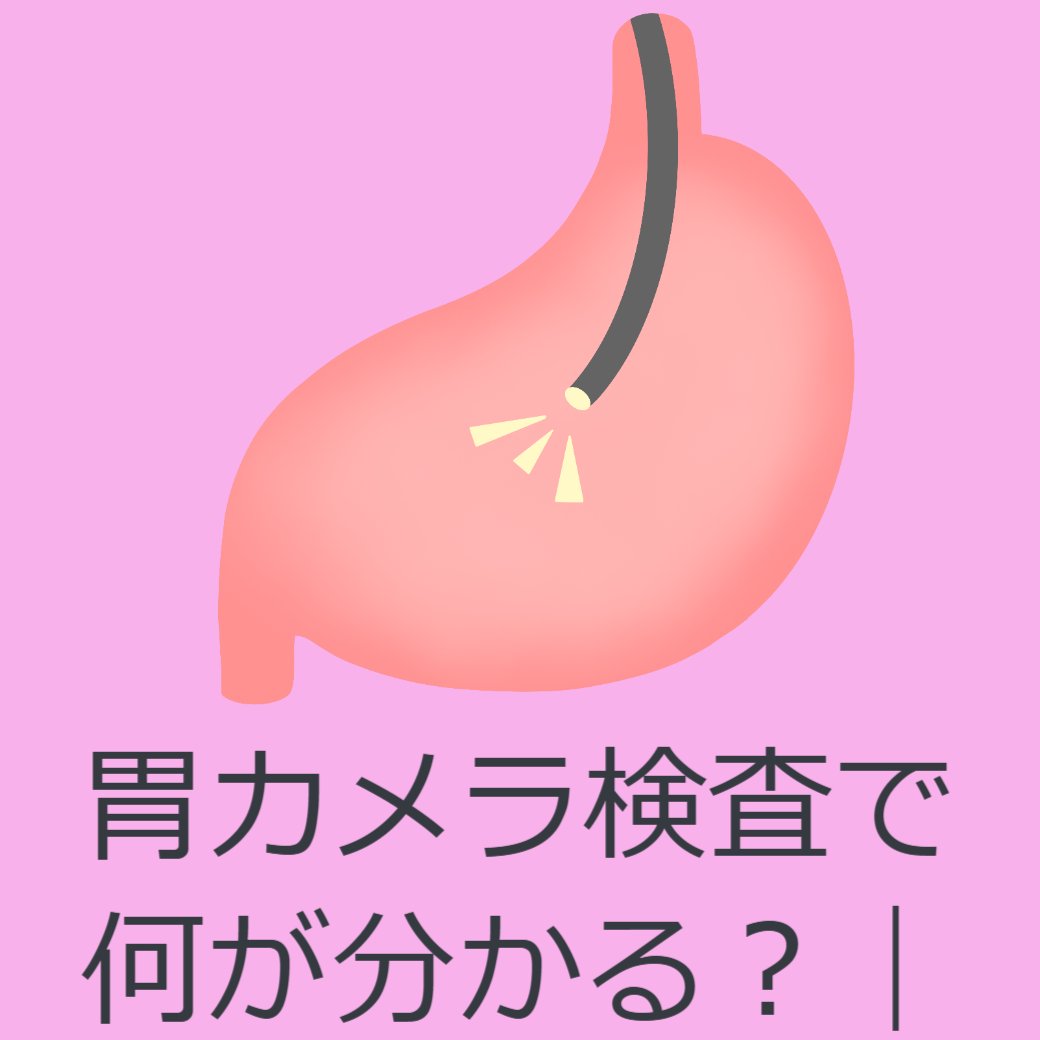2025年9月08日
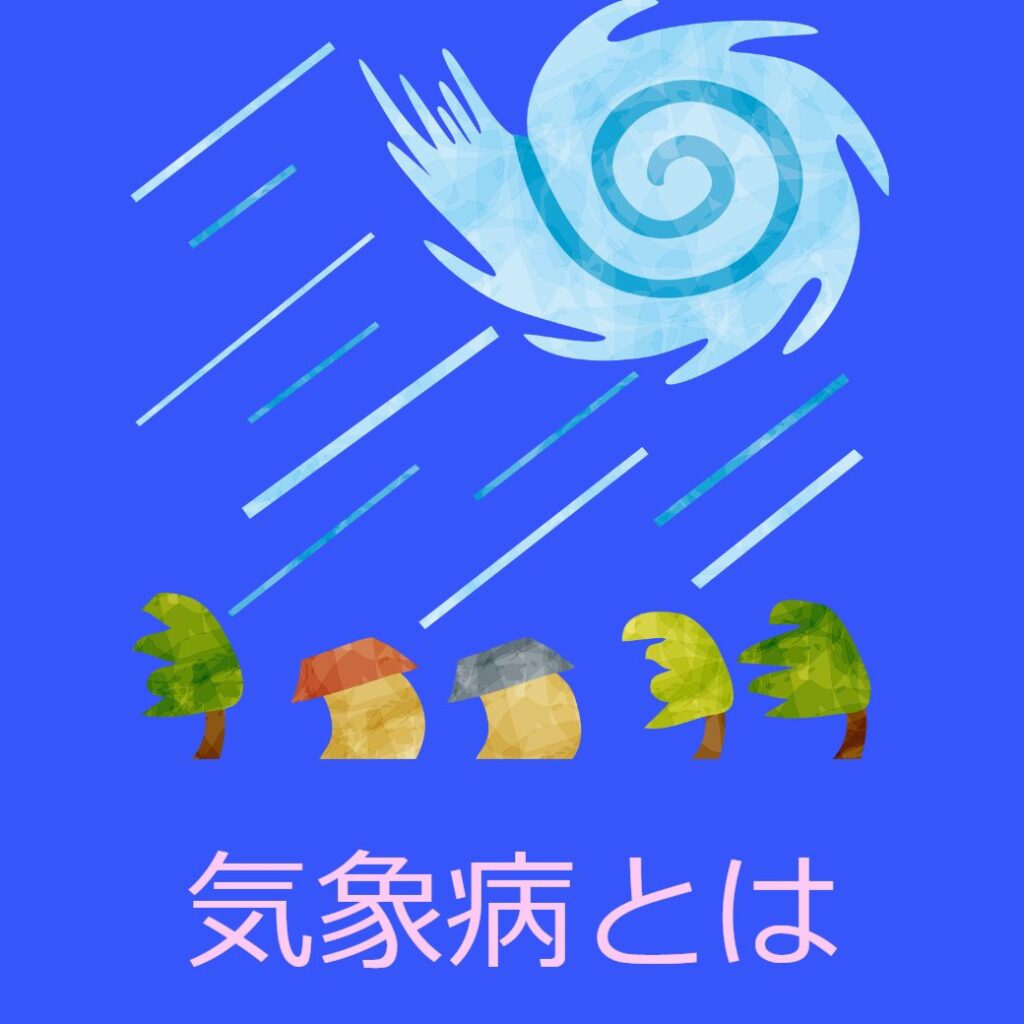
こんにちは。
暑い日が続きますが、9月ともなるとそろそろ台風の時期になってきます。先週発生した台風15号はあっという間に過ぎ去ってしまい大阪府への物的な被害はあまりなかったようです。
ですが台風が発生すると気圧が下がります。低気圧による不調を感じる方も多いのではないでしょうか?今回は、気象病についてお伝えしたいと思います。
よかったら見てみてください。
気象病とは
気温や気圧などの気候の変化によって引き起こされるさまざまな症状の総称です。
特に、梅雨や台風の時期、季節の変わり目など、気候が変わりやすい時期に症状が出やすく、頭痛、めまい、耳鳴り、胃腸の不調、動悸、不眠、気持ちの落ち込み、倦怠感、関節痛、肩こり、腰痛など、様々な症状が現れることがあります。
気象病セルフチェック
□天気の変化を敏感に察知する
□「もうすぐ雨が降りそう」「気圧が変化しそう」というのがなんとなくわかる
□気圧の変化により気分が浮き沈みしやすい
□過去に骨折やけがをしたところが時々痛む
□雨が降る前に眠気やめまいを感じやすい
□湿気が多いと胃腸の調子が悪くなる
□春や秋、梅雨など季節の変わり目に体調を崩しやすい
□暑い季節に屋外に出ると具合が悪くなり、寒い季節には冷えがつらい
以上の項目で該当するものが複数ある場合には、気象病の可能性が高いかもしれません。
どうして気象病になるのか?
私たちの身体は自律神経のバランスによってその恒常性が保たれています。交感神経が体を活動モードにする一方、副交感神経がリラックスモードにすることで、そのバランスが保たれます。
しかし、ストレスを強く感じる環境下に置かれたり、生活リズムが崩れている場合には自律神経のバランスが乱れやすくなり、気象の変化に敏感に反応しやすくなります。また、気象の変化自体がストレスになり、自律神経のバランスを乱す原因にもなります。
内耳の影響
中でも気圧は不調に大きく影響します。気圧が下がると内耳のバランスと視覚にずれが生じ、脳がそのずれを調整できないと、めまいなどの不調が生じると考えられています。内耳とは、耳の奥にある器官です。音を感じる聴覚器官である他、体のバランスを維持するために働く平衡感覚を保つ部位でもあります。さらに内耳には、気圧を感知する働きもあると言われています。気圧は目に見えないですが、気圧変動による内耳の平衡感覚と視覚のバランスの乱れは、体に大きな負担となります。
血管の拡張
低気圧下では空気中の酸素濃度が低下し、血液中の酸素が薄くなってしまうことがあります。すると、体は血管を拡張させて酸素を行き渡らせようとします。拡がった血管は神経を刺激し、痛みの一因となります。
姿勢
気象病と診断される人の中には、姿勢の悪さが目立つ人が少なくありません。猫背や反り腰、ストレートネックなどの姿勢の悪さは、骨格のゆがみも生じさせます。すると、筋肉のバランスが崩れたり、特定の部位が強く緊張したりして、頭痛やめまいなどの症状が現れることがあります。
治療
気象病は天候というヒトの力では改善することができない現象が根本的な原因であるため、治療はそれぞれの症状を改善する対症療法が主体となります。
一方で、低気圧のときなどに併せて強い体調の変化が現れるようなケースでは、事前にそれらの症状を予防するための薬物療法などが行われることも少なくありません。特に内耳の血流を改善する抗めまい薬や体内の水分循環を改善する五苓散などの漢方薬がよく使用されます。また、ストレスや疲れ、睡眠不足など不規則な生活習慣も気象病による自律神経の乱れなどを助長することがあるので、発症を予防するための生活習慣改善も大きなポイントです。
予防と対策
・水分や塩分の摂りすぎに注意する
・お風呂は、湯船につかり自律神経を整える
・ストレッチで血行改善を促す
・締め付けない厚手の衣類を着る
古傷が痛むという言葉があるように、天候の変化により体の弱い部分の症状が起こることが多いです。ストレッチをしたり、リラックスするなど一息いれることをお勧めします。
いかがでしたか?
毎年「なんとなくつらい」と感じる時期がある人は、気象病の可能性があるかもしれません。
つらいと感じる時に、同じ条件が重なっていることがないか一度考えてみましょう。基本的には対症療法となりますが、つらいと感じたら抱え込まず一度ご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。