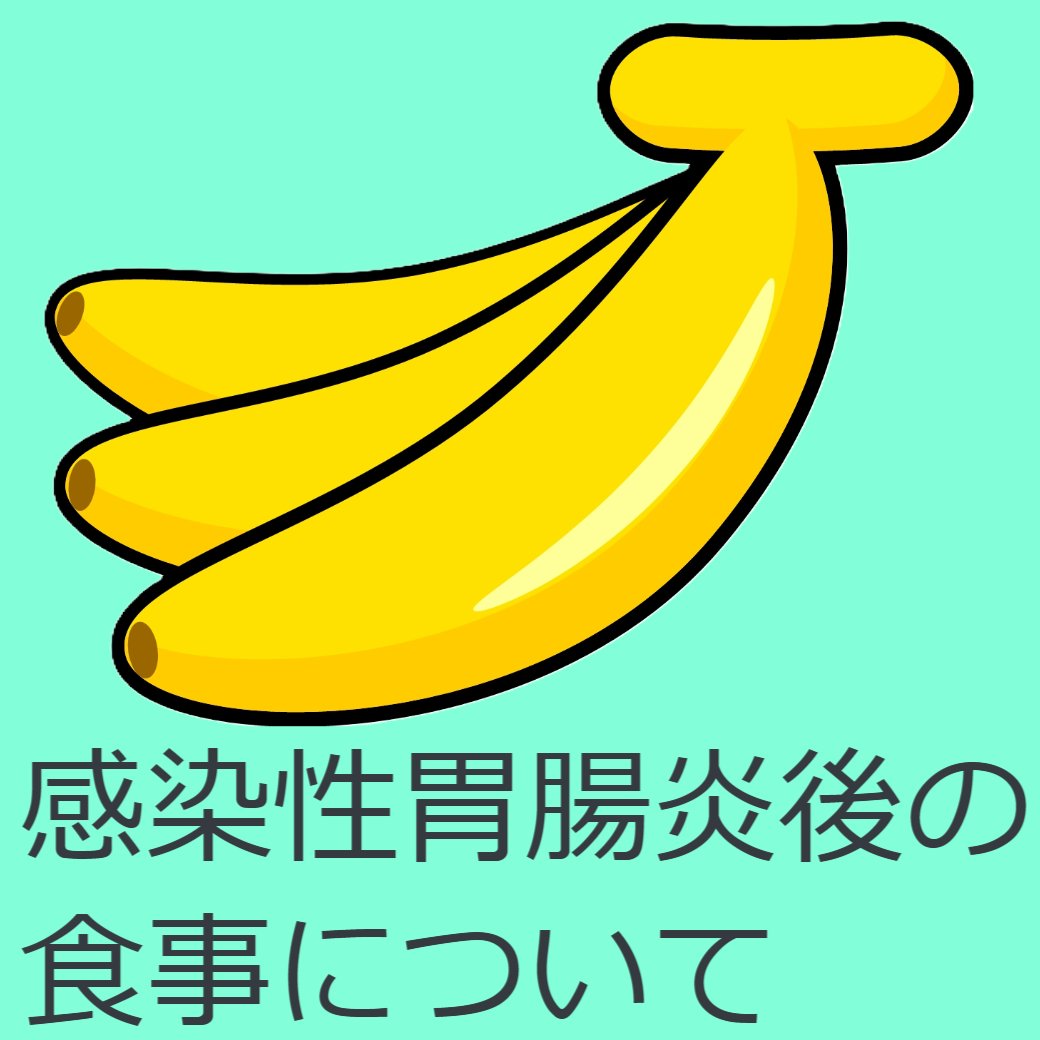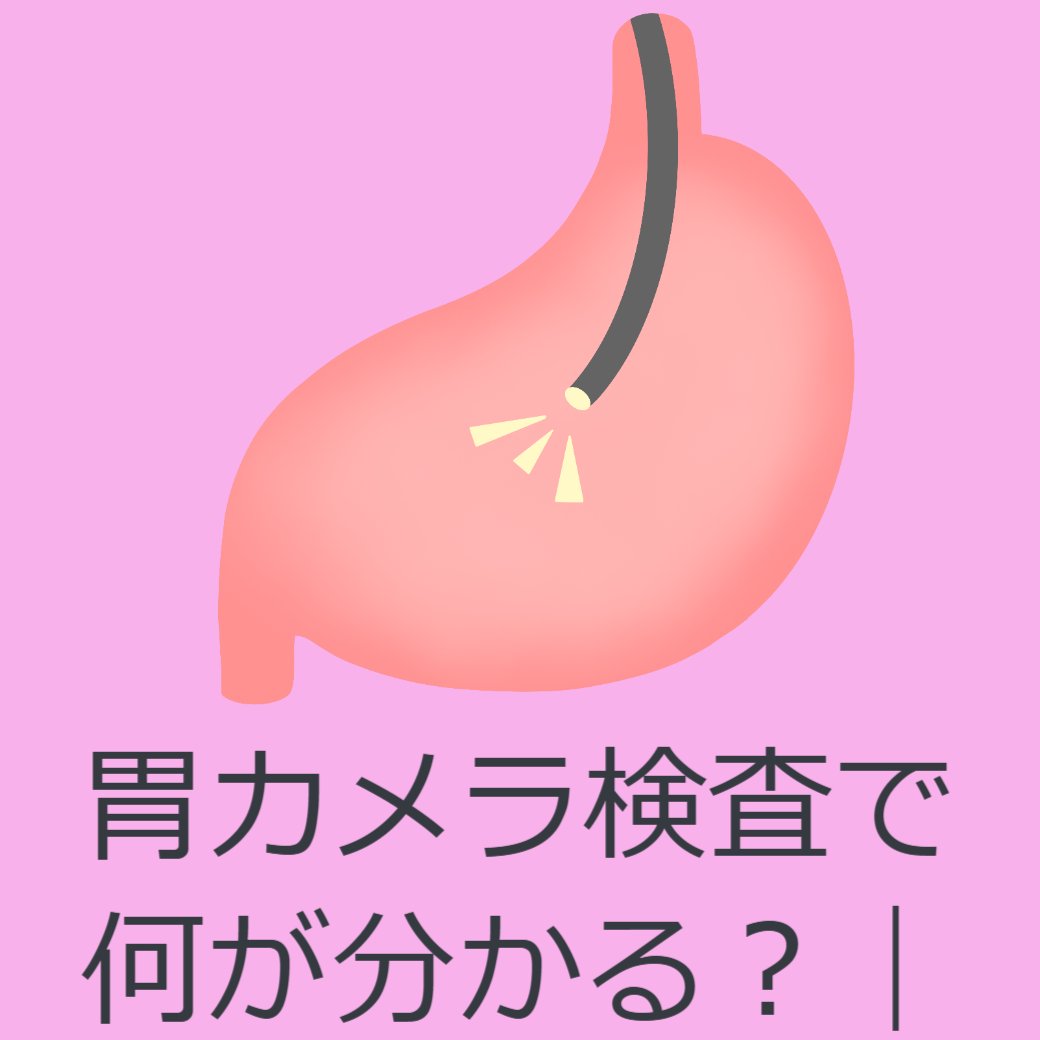2025年8月25日
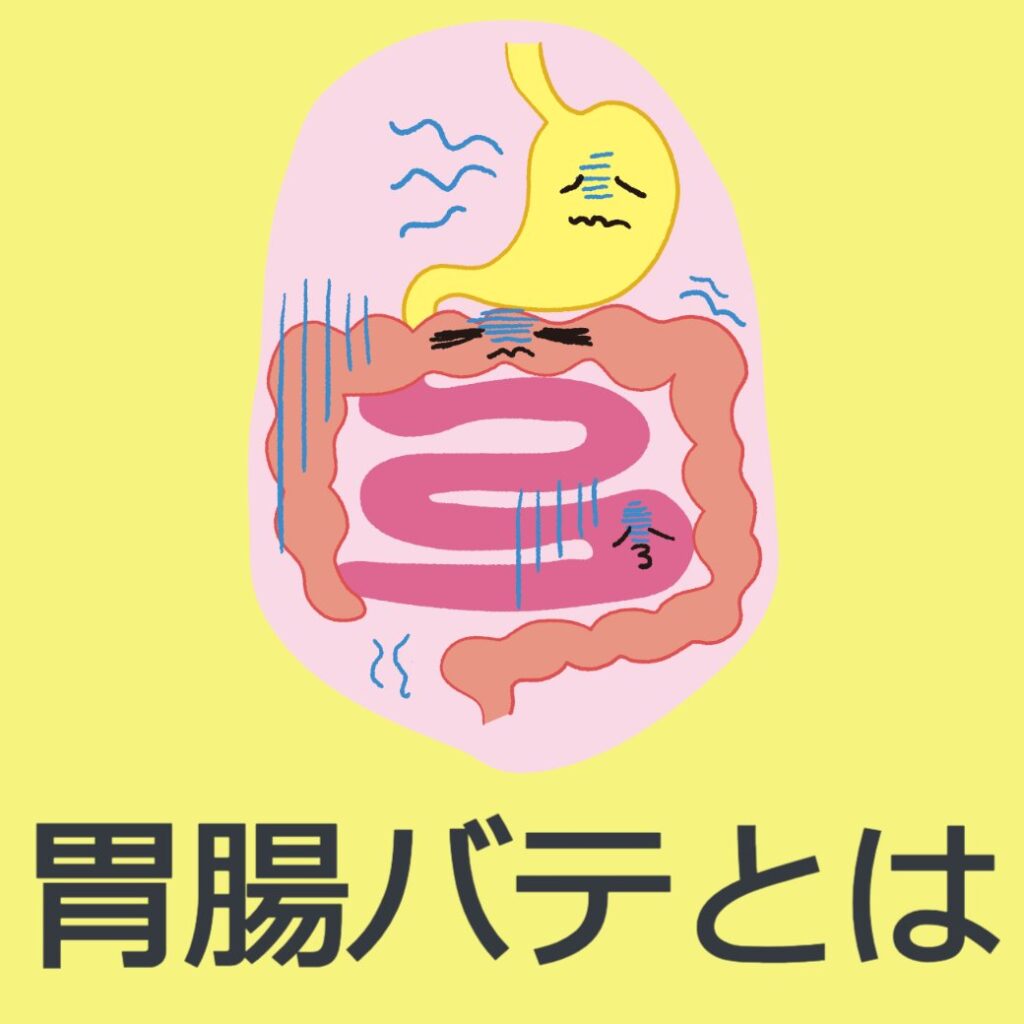
こんにちは。ひらたクリニックです。
暑い日が毎日続きますね。こんなに暑いと冷たい物を摂りたくなりますよね。
近年の日本の夏は、異常とも思えるほどの酷暑となっています。夏バテになっていませんか?
今回は、夏バテについてお伝えしたいと思います。
夏バテとは?
夏バテの代表的な症状は、全身のだるさと疲労感です。なんとなく体がだるく、疲れが取れにくい日が続きます。また、食欲不振や頭痛などが起こります。さらに暑さによって睡眠不足になることも少なくありません。夏バテは、体力を奪われるだけでなく、胃や腸の不調にも影響を与えます。
夏バテが引き起こす『胃腸バテ』とは?
連日うだるような暑さが続き、夏バテ気味の方も多いのではないでしょうか。
夏バテの症状のひとつに食欲がなくなるというものがありますが、こちらは胃腸の不調である『胃腸バテ』の症状です。
夏場の胃腸バテの一番の原因と言われているのは、自律神経の乱れです。夏は暑い室外と冷房で冷えた室内との急激な温度差で、自律神経が乱れやすくなります。自律神経の乱れにより、胃の働きが全体的に低下して消化が悪くなったり、胃酸の分泌が過剰になって胃の粘膜を荒らしてしまうことにより、食欲不振や胃もたれといった症状が引き起こされます。
他にも、夏場は冷たい食べ物や飲み物に手が伸びがちですが、冷たい物ばかり食べたり飲んだりしていると胃腸が冷えすぎて機能が低下し、胃もたれや下痢を引き起こします。
自律神経が乱れる『冷房バテ』
人の身体は「温熱順化」といって、徐々に暑さに慣れていくようにできています。しかしここ近年は、気候の変動もあり、まだ暑さに慣れていない時期から猛暑日になることもあります。そうなると冷房をつけて、設定温度も低めになります。涼しい室内と暑い室外を行き来することでその温度差によって自律神経が乱れ、内臓の働きが鈍くなり、疲れがたまりやすくなってしまいます。
また、屋内と屋外の行き来がなくても、冷房の効いた室内に一日中いるという人は、体が冷え切って血行が悪くなり、内臓の働きが落ちたり、肩こりなどを引き起こしがちです。屋内にいる時は、羽織るものや膝掛けを準備し冷えすぎないようにしましょう。
冷たい食べ物で『食冷えバテ』
キンキンに冷えたアルコールやジュース、アイスやかき氷など、夏になるとつい冷たい食べ物や飲み物を摂ってしまいます。しかし冷房の効いた屋内にいることが多い人がこうした食べ物、飲み物ばかりを摂っていると、胃腸が冷えて機能が低下し、胃もたれや下痢を起こすことになります。暑い夏でも身体のためには、冷えた飲食物は避けた方が良いでしょう。
薄着は禁物
猛暑から薄着をしがちですが、冷房が効いた屋内では羽織れるガーディガンなどを常備しておくようにしましょう。また足元も冷えますので靴下を準備しておくこともひとつです。
夏でも湯船に浸かる
夏の入浴はシャワーで済ませるという方も多いと思います。しかし、夏もしっかり湯船に浸かることが大切です。屋外が暑いため自覚できない人も多いのですが、身体は冷房で冷えきっています。
ただし、40℃を超える熱い湯に浸かると交感神経が優位になり、寝付きにくくなってしまいます。38℃程度のぬるめの湯に最低10分、できれば30分くらい浸かると副交感神経が優位になりリラックスできます。自律神経のバランスが整い心身が元気になります。
寝る前は明かりを暗めにしましょう
寝る直前まで強い光を浴びていると、自律神経のバランスが崩れてしまいます。強い光には、自然な眠りへと誘う働きをもつメラトニンの分泌を抑える作用があります。寝る1時間前くらいにはパソコンやスマホの作業は終え、部屋の明かりを暗めにしましょう。
身体を温める食材を摂りましょう
胃腸バテになったら、まず食事に薬味やスパイスを取り入れて胃腸を温めていきましょう。
そうめんや冷奴などの冷たい物を食べる時に、生姜やネギ、みょうがなどの胃腸を温める作用のある薬味を一緒に摂るのがおすすめです。また、冷たいものを摂取した後は、常温の飲料や温かい白湯などをのむと胃腸の冷えを和らげることができます。
また、夏場は水分補給が大切ですが、摂りすぎも問題です。水には熱を奪う性質があり、冷えの原因にもなるので、適正量を心がけましょう。
スタミナ=肉ではない
胃腸バテで胃腸が弱っている時に、スタミナをつけようと、脂たっぷりの肉や鰻を食べると余計に胃腸に負担がかかり、逆効果となります。疲労回復効果のあるビタミンB1は、豚肉に豊富と言われますが、ビタミンB1は、玄米やタイ、カツオ、マグロなどの魚にも入っています。豆腐にも豊富に含まれていますので、枝豆などもお勧めです。
また、タマネギ、ニンニク、ネギなどにはアリシンという成分が含まれますが、アリシンがビタミンB1と結合すると体内への吸収がよくなり、疲労回復効果が高まります。ニンニクやネギなどを上記の食材に合わせると、スタミナアップに効果的です。
いかがでしたか?
近年の夏は酷暑であり、今まで体力に自信があった方もバテ気味だと思います。冷たい物ばかり摂取せず、暑い時には熱い物を、ということもいいことかもしれません。
またのどの渇きは脱水の証拠なので、渇きを感じる前に時間を決めて定期的に水分を摂るようにしましょう。高齢になると脱水が起こっていてものどの渇きを感じないことがあるので、こまめに水分摂取と適度な塩分を摂るように心がけましょう。無理をしない範囲で夏場を乗り越えたいものです。
最後までお読みいただきありがとうございました。