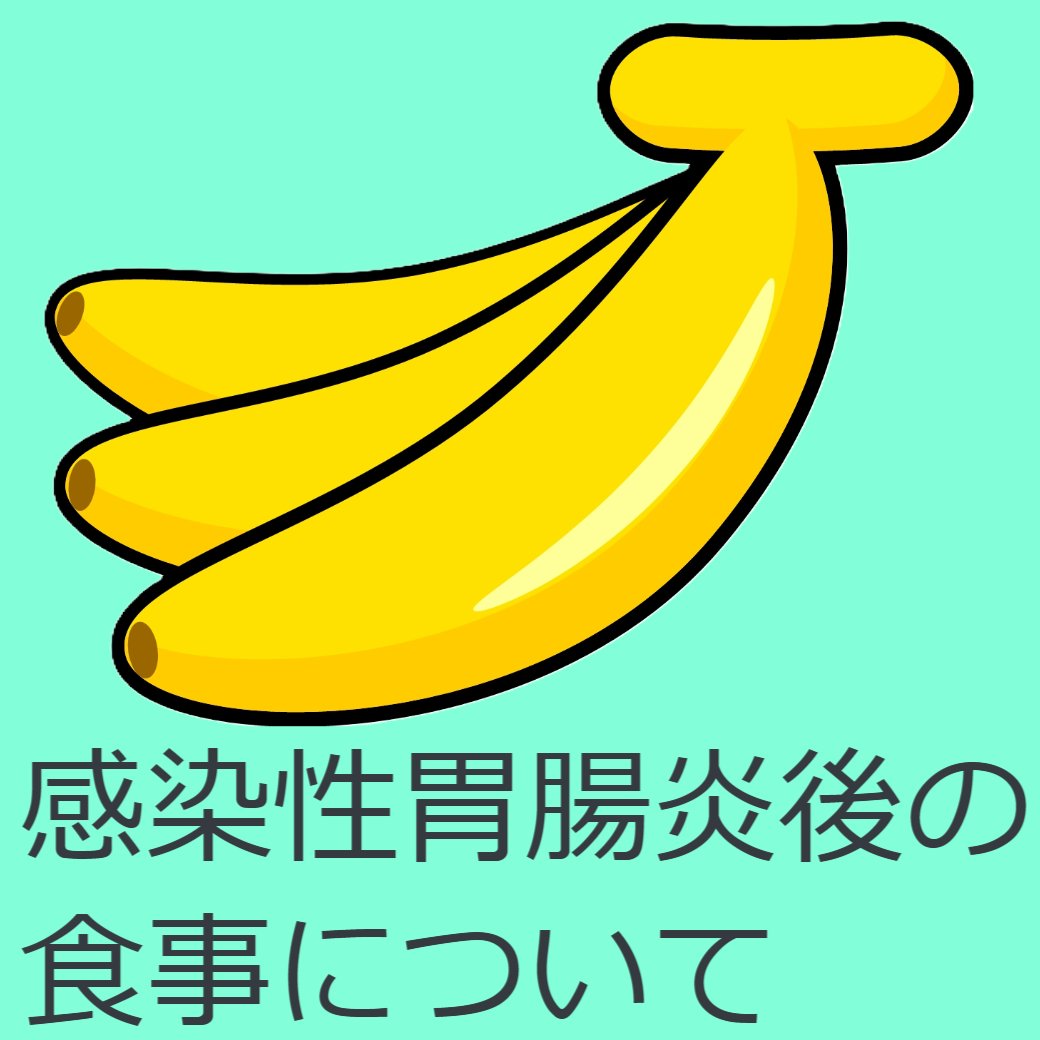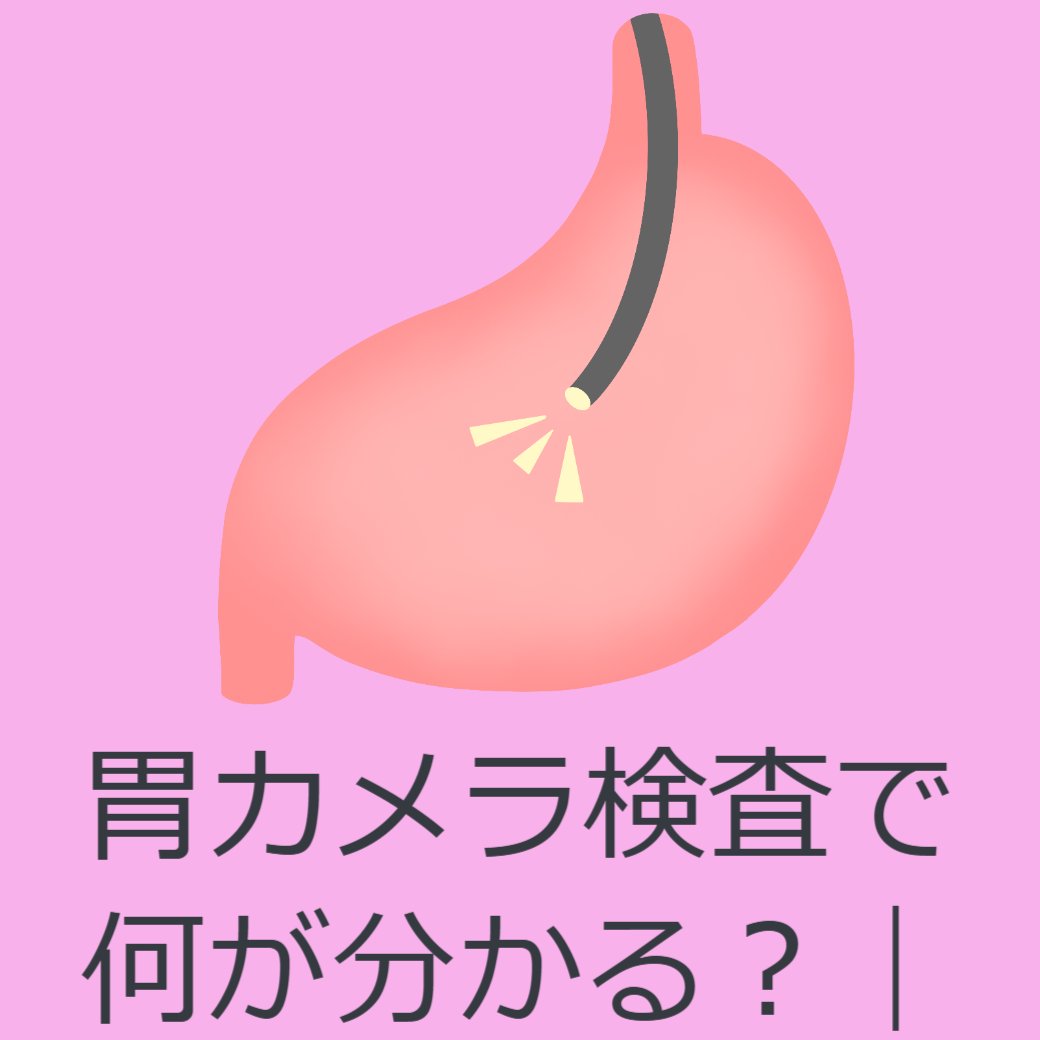2025年7月28日
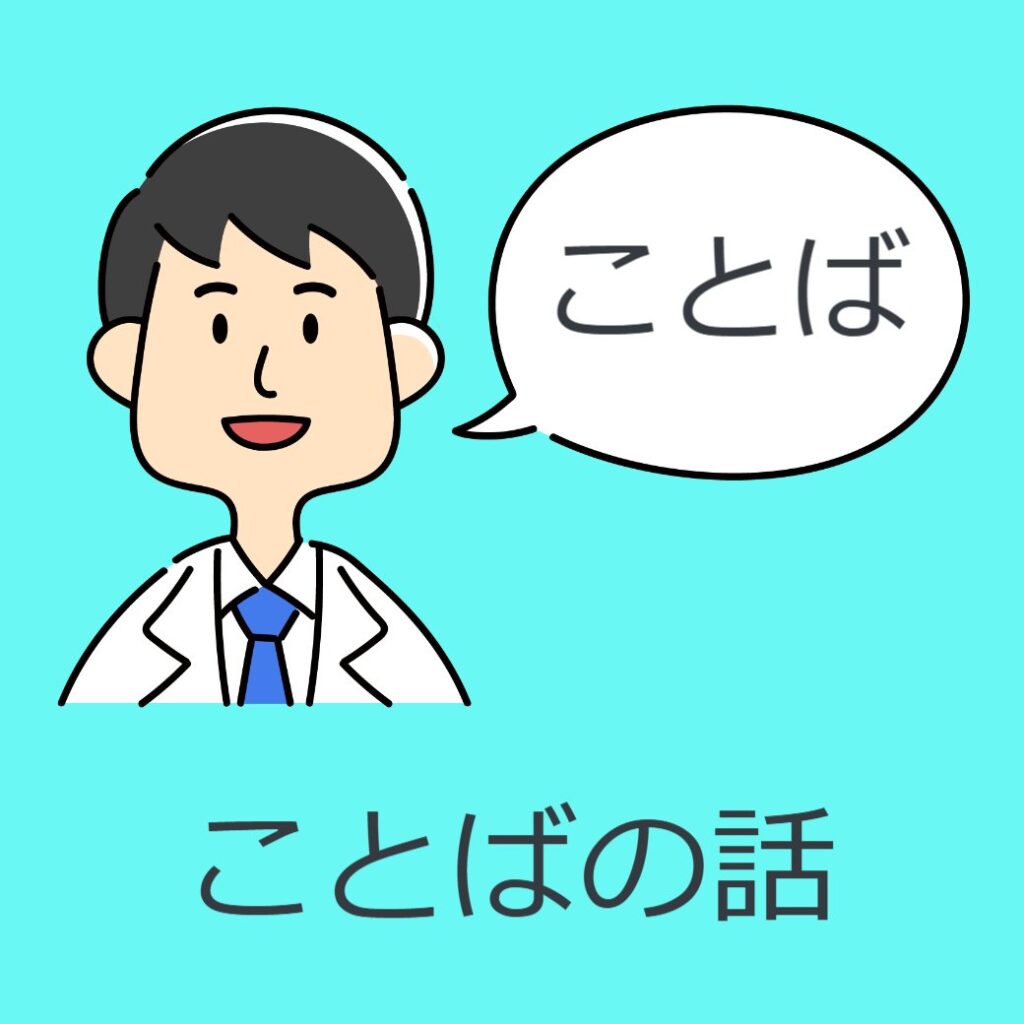
こんにちは。
ひらたクリニック副院長の井口です。
記録的な猛暑が続いていますが、体調管理をしっかりしていきましょう。
さて本日のブログはことばの話です。良かったら最後までお読みください。
塾での話
私が小学5年生の頃、親戚が塾に通い始めた事から、週末に塾へ行かされる様になりました。それまで週末は、ずっと、カブスカウト(ボーイスカウトのジュニア版)に通っていたのですが、両立が難しく、止めさせられ、電話帳みたいな問題集と国語辞典みたいな参考書をもって塾に通わされました。
その頃は「スパルタ教育」やら「教育ママ」などの言葉が日常を踊っていた時期であり、当時の塾では宿題を忘れたり、テストで点数が悪いと、ビンタをされるのが当たり前の時代でした。
そんな塾の社会科で「白村江の戦い」の読みがなを書けという問題がでました。
社会科は、聞かれた事を知らなければ何も答えられない上、他の教科に比べて先生のビンタも痛いという恐怖の教科でした。
そんな社会科のテストで、あと1問答えられなければビンタという状態でこの問題が現れました。
「なぜ、社会科で漢字の読み方の問題があるのだろう?」と思いながら、他に読み方が分らず、「はくそんこう」と解答を書いた訳ですが、見事にビンタを受ける事になりました。
「白村江の戦い」とは6世紀の朝鮮で起こった戦争で唐+新羅 (中国+朝鮮)連合軍と倭+百済(日本+朝鮮)連合軍の戦争で倭+百済(日本+朝鮮)連合軍が敗退します。コレが歴史的に、どう重要かは知らないですが、「白村江=はくすきのえ」と言う漢字の読みにくさから、その後も塾のテストにたびたび登場した事を覚えています。
白村江の戦い
そんな、今でも根に持つぐらい覚えている「白村江の戦い」ですが、先日、テレビで「はくそんこう」と紹介されていました。
塾とはいえ、小学生に答えさせる様な「はくすきのえ」を「はくそんこう」と読み間違えるなんて、「最近のテレビは質が落ちたなぁ」と思っていたのですが、解説によると、最近は「はくそんこう」と読む様になったとの事でした。
もともと、「はくすきのえ」と読む経緯があった訳で、新たに歴史的発見があった訳でもないのになぜ、読み方を変えたのだろうかと疑問に思っていました。
「ゆとり教育の弊害か?」とも思っていましたが、よくよく調べると、スゴい長い目で見れば「みんなが間違って読むのであれば、間違った読み方も正解にしよう」という動きが日本語では良くある様です。
たとえば、「依存」とか、「間髪」とか、「十匹」とかで、元々は「いそん」、「かんはつ」、「じっぴき」と読んでいましたが、今では「いぞん」、「かんぱつ」、「じゅっぴき」の方が主流になっています。独眼竜でおなじみの伊達氏ももともとは「いだて」と呼ばれていたものが「いまだ→まだ」「いだく→だく」と同じような脱「い」音変化で「だて」になったと言われている様です。
他にも「微妙」の様に、違った意味が一般的になってしまったために、元の意味とは違った意味で用いられるようになった言葉などもあります。
下血と血便の違い
私が研修医の頃、消化器内科の指導医に「下血」と「血便」の違いについて質問された事があります。
「下血」は液体で、「血便」は固体のイメージで、「下血」はお尻からでる血液で、「血便」は血の混じった便と答えましたが、正解は、「下血」は「上部消化管の出血」で、「血便」は「下部消化管の出血」を表すとの事でした。
この時の私と同じように表現される方は、研修医や患者さんはもちろんの事、消化器内科以外の内科医の中にも多く、一般的なイメージもこの時の私と同じものだと思います。
「上部消化管出血」は、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、上部小腸の粘膜傷害からの出血で、血液が胃酸などの消化液で消化されるため、黒色便やタール便と呼ばれるようなモノクロなうんちがおしりからでてきます。イメージとしては海苔の佃煮で、もっとわかりやすく言うと「ごはんですよ」です。
鼻血や食道からの出血も、おしりから出た場合は「上部消化管出血」に含まれるため、「下血」となりますが、これらはどっちかと言えば口から吐いたり、鼻から垂れたりするため、そのまま、「吐血」や「鼻出血」と表します。
「下部消化管出血」は、大腸からの出血で、暗赤色、鮮血色、紫色など、基本赤系の色のうんちが出てきます。原因としては、やはり「痔核」が一番多く、他には「虚血性腸炎」、「憩室出血」などが多いです。
医療の世界も変化が
話は元に戻って、元々は欧米で使用されていた「メレナ」という言葉を日本語に訳した際に「下血」と名付けられました。
メレナとは血液が消化されて黒色となったものでタール便や黒色便とも呼ばれます。と言う様にもろに上部消化管出血の事を指しています。
「血便」は名前の通りであり、下部消化管出血の事を指す言葉とした様です。
こういう歴史をもとに「下血は上部消化管出血」「血便は下部消化管出血」と言う様になったそうです。
私はこの話を先輩に聞いてから、言い伝えのように後輩にも伝えていましたが、ある時、後輩から偉い先生の書いた文章に、お尻からでている赤い血を「下血」との記載があると、指摘を受けました。
実際にその文章も拝見しましたが、どう読んでも、そうとしか取れない記載であり、解釈の違いでそう受け取れるという類いのものではありませんでした。
また、私などとは比べるべくもない素晴らしい肩書きの先生の記述であり、「医学用語の意味も時代によって移り変わって行くのだな」と時の流れを感じました。
とは言え、専門の先生に間違っていると取られかねない用語で紹介状などを書いて「レベルの低い医師だな」などと思われると、自分が馬鹿にされるだけならまだしも、紹介した患者さんの不利益に繋がることもあるので、こう言う用語にも注意を払っていきたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました。